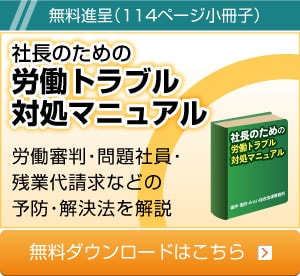会社の経営状態が悪くなっても原則として行ってはいけないこと
会社の経営が苦しくなり、取引先等への支払いが滞っている状態で、会社所有不動産の名義を、贈与や売買を原因として、会社の役員や、近親者、その他知人などの関係者のものにかえることは原則として許されません。
また、会社がそのような状態である中、会社の一部の懇意にしている取引先(債権者)にのみ、支払いの代わりに不動産を贈与するということ(代物弁済)も行ってはなりませんし、一部の債権者のために不動産に抵当権を設定することも許されません。
このような贈与・売買・代物弁済・抵当権の設定は、「詐害行為」として、民法の適用により、後になって効力が否定される(取り消される)可能性が高いものとなります(詐害行為取消)。
詐害行為取消で考慮される要素としては、1. 責任財産の保全、2. 債権者間の公平、3. 債務者にとっての有用性です。
- 責任財産の保全とは、会社の財産を減少させる会社の行為を否認することで、財産の回復を図り債権者による強制執行に備えるというものです。
- 債権者間の公平とは、取引先等の債権者は公平でなければならず、一部の債権者にのみ優先的に弁済がなされてはならないという考え方です。
- 債務者にとっての有用性とは、1. と 2.の要素を考慮しても、会社にとって有用であると判断される場合があるとする考え方です。
贈与という無償で相手に譲り渡す行為はもちろんのこと、売買のように対価を伴う譲渡し行為であっても、不動産を金銭という散逸されやすい財産に変えることは、会社の財産を実質的に減少させることになるため、債権者を害する行為とされ、原則として許されないのです。
また、代物弁済についても、他の債権者から配当の機会を奪う可能性が高まることから、たとえ適正価格であっても、債権者を害する行為とされています。
抵当権の設定も、抵当権者に優先弁済権を与える反面、他の債権者から配当の機会を奪うこととなるため、許されないこととなります。
具体的な効果
効力が否定されるとは、具体的には、贈与・売買・代物弁済を受けた譲受人が未だその不動産を所有している場合は、当該不動産の所有権・名義が会社の下に戻されることとなります(この場合、移転登記手続にかけた費用等が無駄になってしまいます)。
また、譲受人が、既に事情を全く知らない第三者に当該不動産を売ってしまっている場合、譲受人は当該不動産価値に相当する金員を、債権者に支払わなければならないこととなります。
抵当権が設定されている場合は、抵当権設定登記の抹消登記手続が行われます。
なお、この効力否定の手続は、訴訟提起によって行われます。
ですので、譲受人等は「訴えられる」という不利益も受けることになります。
例外的に詐害行為とされない場合
例外的に、このような売買による名義変更が許されるのは、「有用の資」に充てるための売却であり、それが適正価格であると評価される場合です。
たとえば「事業資金に充てるために」、当該不動産を、「適正価格で」売却した場合等です。
適正価格であったこと、有用の資に充てたことは譲受人が立証責任を負うことになります。
ですので、後に争いとなることを避けるためにも、不動産価格の見積もりは2、3社に頼み、証拠として見積もり結果の書面を残しておいた上で、その売却代金がどのように使われたかも明確にしておくほうが良いでしょう。
なお、不動産の譲受人、抵当権者が、会社の経営状態が悪いことや、取引先等の債権者がいることを全く知らなかった場合は、不動産の取戻しや、金員の支払い、抵当権抹消を免れます。
しかし、会社の役員や、近親者、その他知人などの関係者、懇意にしている取引先等が譲受人・抵当権者となっている場合、会社の経営状態等を知っていたと考えられるので、このような事情を全く知らなかったとの立証は一般的には困難です。
破産手続が開始した場合
会社が破産手続に入った場合、破産会社が破産手続開始前に行った破産債権者(取引先等)を害する行為の効力を、破産財団との関係で否認して、破産財団の状態を回復する、否認権が行使される場合があります。
破産管財人による「否認」がなされ、詐害行為の場合と同様、不動産の取戻しや、金員の返還を求められることとなります。